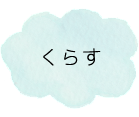001

二代目沖光・原 寛さん(隠岐沖光刃物)

プロフィール

原 寛(はら・ひろし)
大正14年(1925年)より60年にわたり、ヤスギハガネの最高級刃物鋼白紙印を原料とした打刃物を作り続けてきた「隠岐沖光刃物」の二代目。物心がついたときから、父の鍛冶業を手伝い、「ふいご」を吹くことを日課として育った。 太平洋戦争が始まってから終戦までは、先代の父親と内弟子、刀専門の研ぎ師など6名で軍刀をつくり軍に納めた。 沖光による打刃物(各種包丁類・大工用刃物など)は、日本刀の場合と同様、古式にのっとった鍛錬法を用いており、鍛錬や焼入れなどの燃料は、全て松木炭を使用している。 平成13年(2001年)、「しまねの伝統工芸」に指定される。平成22年(2010年)には、初代「沖光」が昭和27年(1952年)に制作した「講話記念刀(太刀)」が「西ノ島町指定文化財(有形文化財)」に指定された。
子どもの頃の思い出
私が物心ついたときには、子どもは学校へ行ったら一心不乱に勉強し、帰ってきたら必ず親の手伝いをすることになっていたんです。サッカーみたいな遊びはまったく無かったですね。とにかく帰ってきたら、牛を連れて山へ行って草を食べさすみたいな、親の手伝いをしていたなかで育ってきました。私の場合は、親が鍛冶屋だったから、学校から帰ってきたら「ふいご」を吹く役でしたね。それが日課になってました。勉強したいけど勉強するというのは贅沢なもので、学校にいったらやってもいいけど、帰ってきたら親の手伝いをしなきゃいけない。そういう中で育ってきたような気がしています。

だから、子どもの頃の思い出というものは、ふいごをひっぱることですね。なぜふいごをひっぱるかというと、量産するために、焼けた鉄(かね)をひっぱりだす。そして向打(むこうち)に打たして、親父と向打(むこうち)が一生懸命叩いている間に、子どもはふいごを吹きながら、鉄(かね)の焼け具合をみて、次に引っ張り出すちょうどいい温度に間に合わせるように焼かないけん。それを失敗すると、鉄(かね)は溶けて流れてなくなってしまう。その温度が足らなくて、鉄(かね)が硬いままだったら、叩いても伸びないから、ちょうど良いように焼くためにコツみたいなものを仕込まれとった。うまく焼けたときには親父が褒めてくれる。「よーし、いいぞ!これだこれだ!」と囃しをかけながらやってくれる。ところが、それが毎日の日課になりますと、なんとかしてサボってやろうと思う気持ちも出てきましたけれど、それはできなかったですね(笑)
時代の変遷と軍刀づくり

鍛治の手伝いをしてきたのは尋常学校まで、高等科になると今度は時代が全く変わってきて、第2次世界大戦、太平洋戦争が始まるようになる。昭和16年12月8日に太平洋戦争が始まって、真珠湾攻撃が始まったのをいまでも覚えていますけれど。 その時点になると、包丁や鎌みたいのを作っていたのを、鍛治の経営の内容をがらっと変えまして、軍刀を作るようになりました。とにかく、日本の政府に協力して、政府・軍の言う通りに軍刀をつくって、小倉陸軍造兵廠という陸軍に将校用軍刀を納める仕事に切り替えたんですね。 その時点では、男のいわゆる内弟子が3名、刀専門の研ぎ師、徴用を逃れるための熟練職人弟子と親父を加えて6名でやってました。月に15振りくらいの割り当てを受けて、軍に納めてました。玉鋼は島根県の山中から産出されるものが、軍刀を作るにしたがって送ってきよったんですけど。そういう仕事を毎日繰り返して終戦を迎えました。
鍛治職と後継者
自分の仕事の後継を、子どもが継いでいなくて、後継者でないということが証明しておりますように、結局、鍛治そのものだけで生活を支えるということは大変なことですね。ですから、子どもが物心ついたときに、小学校1年生くらいの頃に「お父さん、僕も一緒にやるよ」と張り切っておったんですけれど、やっぱり小学校3年生、4年生になりますと、周囲の子どもたちとの情報交換が始まりますね。「いや、俺は大きくなったら、大きな船の船長になる」とか「医者になる」とか。そういった理想を高く掲げて、みんな話し合いますね。

だから、自分で物心がついて、こういう方向で行きたい、という「さだめ」は、子ども自身がお互いに持つようになってきます。それは、私は正常な発育だと思います。屁理屈を言うようですけども、親の背中を見て育つというのは、それは事実としても、だからといって、親が鍛治しとったから鍛冶屋になれということは、今の時点では言えないなぁと思っています。自分自身はそれでよかったんだと思ってます。親と一緒にやっとっても、これはどうやっても飯が食えないぞと思って、自分はこういう方向でやってみたいと、それぞれの方向づけを自分たちで責任もってやっていくというのが大事ですね。私の生涯とは、なんだったのかなぁと考えますと、やっぱり無我夢中で子供を育てることが、ひとつの生きがいになっとったかなぁと思ってます。いま、それぞれに子どもたちが落ち着いてくれたから、最終的に自分の生涯を振り返ったときには、これでよかったんだなぁという考え方をしています。いま沖光刃物の後継者がいないということの言い訳にはなりませんけども、実際は子どもたちもみなそれぞれ目標を定めて、自分なりに精一杯努力することが、一番やりがいのある仕事なのではないかなぁと思っとります。
長く愛される沖光刃物

私は偶然かもしれんけど、50年くらい前に作った包丁が1本ありまして、それをいまも時々使います。刃先にうっすらと鋼が残っていて、いまでも使ってもよく切れるんですね。鋼の本質の切れ味というものは、そのあたりにありますね。(新しい包丁と50年間使った包丁を取り出して)刃物はずっと研いで使えます。研ぐたびに少しずつ細くなっていきます。刃がほとんど全部に入ってるから、いくら研いでも使えるんですね。先だけに刃が入っていると、その部分だけしか使えないんですよ。鉄を割って、その中に刃を入れて叩いて、なじませて作っていくんです。
(2017年8月25日 原さんのご自宅にて)
インタビューを終えて(図書館職員のひとこと)
原さんが刃物についてお話されるとき、目を輝かせて、熱く語る姿はとても感動するものがありました。インタビューの中では、沖光刃物の後継者がいなくなってしまったことにも触れられていましたが、やはりどうしても、もったいないなぁと思ってしまいますね。原さんの高い技術や熱い思いを受け継ぐ人が、これから先の未来で現れてくれることを期待してしまいますね。 沖光さんの包丁は自宅でも使っています。とてもよく切れますし、鍬などの農具もとても作業がしやすいですね。いまでも沖光の道具が欲しいとおっしゃる方も多くいらっしゃる理由がよくわかる気がします。
真野理佳